ペットとして人気に高いハムスターとは違い、野生に生息しているネズミは非常に危険な存在です。
家屋への被害や騒音に加え、最も恐ろしいのは健康被害を与える事!
というのも
野生のネズミは体内に、様々な菌やウイルスを保有している可能性が高いんです!
噛まれるだけでなくフンや尿からも感染する恐れがあるため、発見した時は清掃と消毒は必須と言えるでしょう。
では、具体的にどんな病気になってしまうの?
実はネズミが引き起こす健康被害は1つではなく、起こりえる病気は幾つもあるんですよね…。
そこで今回は【ネズミが引き起こす健康被害】について解説していきたいと思います。
- ネズミが保有する菌による感染症
- ネズミが保有するウイルスによる感染症
- ネズミに寄生する害虫被害
ネズミが保有する菌やウイルスによって引き起こされる感染症

まずは、菌やウイルスによって引き起こされる感染症について解説します。
噛まれるだけでなく、排泄物からの空気感染もあり得る事に注意しましょう。
鼠咬症(そこうしょう)
鼠咬症(そこうしょう)とは、ネズミなどのげっ歯類に噛まれることで感染するウイルス病です。
主に
- モニリホルムレンサ桿菌
- 鼠咬症スピリルム
この2種類の病原体を保有したネズミに噛まれたり、引っかかれたりする事で感染してしまうんです。
モニリホルムレンサ桿菌(かんきん)
感染した後、3~5日の潜伏期間を経て
- 悪寒
- 頭痛
- 嘔吐
- 筋肉痛
- 発疹
などの症状が現れ始め、出血や膿を含んだ発疹が出るのが特徴。
進行していくと様々な合併症を引き起こし死に至るケースも存在します。
鼠咬症スピリルム
感染した後、7~20日の長い潜伏期間を経て
- リンパ節の腫れ
- 黒っぽい発疹
- 発熱
などの症状が現れ、発熱と解熱を1~3ヵ月ほど繰り返すのが特徴。
痛みを伴う事は稀ですが、治療しないと死に至るケースも存在します。
いずれの場合もペニシリン系の抗生物質での治療が必要で、ネズミに噛まれたら直ぐに医師の診察を受けるようにして下さい!
レプトスピラ症
レプトスピラ症とは、レプトスピラ菌によって感染する急性熱疾患。
感染経路は感染したネズミの尿や血液などに触れたり、それらが付着した水や土壌に触れた皮膚や粘膜から人間に感染することが知られています。
このため、農業などの水に接する機会が多い方は注意が必要!
一般的に5~14日ほどの潜伏期間を経て
- 発熱
- 悪寒
- 筋肉痛
- 関節痛
- 目の充血
といった初期症状が現れ、発症から1週間ほどすると黄疸や出血が起こり始めます。
また、重症型と言われるワイル病にまで発症するケースがあり、この場合は腎機能障害などが起こることになり適切な処置をしなければ死に至る事になります。
初期症状では見抜く事が困難ですが
黄疸の症状が確認出来たら、すぐに医師の診察を受けるようにして下さい!
予防のためには、ネズミの排泄物に注意することが必要です。

サルモネラ症
サルモネラ症はサルモネラ菌が引き起こすによる感染症で、世界で下痢症を起こす4大原因疾患の一つ。
食中毒の原因としても有名ですよね?
サルモネラ症の一般的な症状は
- 下痢
- 腹痛
- 発熱
- 嘔吐
- 頭痛
- 筋肉痛
ほとんどの場合は症状が軽く、または症状がない場合もあります。
しかし幼児や高齢者となると、脱水症状が重度になりやすく命の危機に陥るケースも存在するため注意が必要。
基本的には食品感染が多いんですが、実はネズミの糞から感染するケースも意外と多いんです!
症状が軽い場合は自然治癒するため特別な治療は必要ありませんが
幼児や高齢者が感染した場合、抗生物質の投与が必要となります!
ハンタウイルス感染症
ハンタウイルス感染症は、げっ歯類が持つハンタウイルスによって引き起こされる感染症で
- 腎症候性出血熱
- ハンタウイルス肺症候群
以上の2つの疾患を起こします。
ハンタウイルス感染症は、主に感染したネズミの排泄物が乾燥し粉じん化したものが風で舞い上がり、人がそれを吸い込むことで感染するんです。
腎症候性出血熱
名前の通り腎臓に障害が起こる疾患で、10~20日の潜伏期間を経て
- 発熱
- 頭痛
- めまい
- 腹痛
- 嘔吐
軽度の症状ならコレだけで回復しますが、重度となると尿の減少・増加といった重度の腎機能障害が起こり、最悪の場合は死に至ります。
ハンタウイルス肺症候群
名前の通り呼吸器に障害が起こる疾患で、1~4週間ほどの長い潜伏期間を経て
- 発熱
- 頭痛
- 悪寒
- 筋肉痛
といった症状が1~4日続き、その後に呼吸困難や酸素欠乏が急速に現れる恐れがあるんです。
死亡率が40%と非常に高く、早期に人工呼吸を用いた集中治療が必要!
ハンタウイルス感染症を予防するためには
ネズミがいる場所での作業時は【マスク】【手袋】【ゴーグル】などの保護具を着用し、十分な換気を行う事で感染予防になります!
また、建物内や家屋周辺のゴミの放置や積み上げなどを避け、定期的な清掃を行うことも必要。

ラッサ熱
ラッサ熱とは、げっ歯類が持つラッサウイルスによって引き起こされる出血を伴う急性ウイルス性疾患です。
このウイルスは、感染した血液や体液を介して人から人への感染も確認されているんです!
感染した人の約80%は発症しませんが、20%の人は6~21日間の潜伏期間を経て
- 発熱
- 頭痛
- 筋肉痛
- 全身倦怠
といった初期症状が現れ、重症化すると消化器官からの出血や血圧低下といった症状が現れ、 肝機能障害や脳炎などの合併症が原因で死亡する事例もあります!
治療にはリブラビリンと呼ばれる抗ウイルス薬が用いられますが効果は限定的…。
つまり現在の医学でも、ラッサ熱に完璧に対応できる薬は存在しないんです!
回復したとしても、難聴や歩行障害といった後遺症が残るケースが多いんですよね…。
こんな厄介なラッサ熱を予防するためには、ネズミ本体と排泄物との接触には適切な防護具を着用することが重要です。
アナフィラキシーショック
アナフィラキシーショックとは【アレルギー反応】の一種で、アレルゲンによって激しくなる重篤なアレルギー反応のことを指します。
アナフィラキシーショックの症状は、アレルゲンの種類・量に加えて個人差がありますが、主な症状として
- 皮膚の腫れ
- 呼吸困難
- 喘息
- 意識障害
- 血圧低下
- 心拍数の増加
といった症状が現れ、重度な場合には数分から数時間で死亡に至ります。
早急な集中治療が必要で、【アドレナリン注射】【抗ヒスタミン剤】【ステロイド剤】などが用いられます。
最近ではコロナワクチンであったり、蜂に刺された時も同じような症状が現れる事で有名ですね。
アナフィラキシーショックを予防するためには、自分がアレルゲンに原因反応する可能性があることを認識することが大切です。
皮膚科ではアレルギー検査であるパッチテストを行ってくれるため、万が一に備えて検査をしておく事も重要です!
【害獣駆除110番】一匹残らず徹底駆除ネズミに寄生する害虫による二次被害

菌やウイルスだけでなく、ネズミ本体を宿主としている害虫たちも存在します。
こういった寄生虫は、宿主が死ぬと他の宿主を探して人間に寄生する事もあるんです。
ツツガムシ
ツツガムシは、ダニの1種でありオリエンティア・ツツガムシ菌を保有する個体に刺される事でのツツガムシ病を発症します。
野生のネズミに寄生するダニの一群に紛れ込んでいる事が多いんです。
ツツガムシ病の症状は、刺されてから5~14日ほどの潜伏期間を経て
- 発熱
- 全身の倦怠感
- 頭痛
- 発疹
39℃を越えるほどの高熱になる事が多く、患者の半数ほどはリンパ節が腫れる症状も見られます。
症急な処置が必要で、治療が遅くなっていまうと播種性血管内凝固により亡くなるケースも多いんです。
予防するためのワクチンなどは存在せず、刺されない事が唯一の予防法となります。
イエダニ
イエダニは、ネズミの体や巣に生息している事が多い吸血性のダニの一種です。
ネズミ意外に鳥にも寄生しますが、宿主が死んでしまうとエサを求めて人間の体に取り付き刺す事がありるんですよね。
イエダニに刺された時の症状は
- 炎症
- 激しい痒み
痒みの症状は蚊に刺された場合を遥かに上回るほど…。
就寝中に襲われる事が多く柔らかい皮膚を好むため、子供や女性の下腹部・太ももなどを刺す事が多いんですよね。
このためエロダニなんて呼ばれています!
さらに恐ろしい被害は、ダニの死骸が喘息や皮膚炎などのアレルギー症状の原因になる事です!
繁殖力も高いため、住みついたイエダニが大量発生していしまう可能性も高いので注意が必要。
イエダニによる症状が繰り返し現れる場合には、徹底的な駆除と適切な医師の診断を受ける事が大事となります。
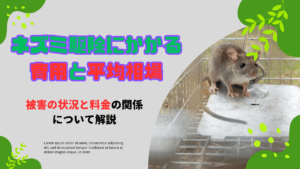
ネズミの被害はプロに任せれば安心
ネズミのが引き起こす健康被害は、噛まれるだけでなく糞や尿からの空気感染もあり得るんです。
このためネズミ本体の駆除はもちろん、排泄物の処理にも最善の注意を払って行う必要があるんですよね。
となると、素人では限界があるのも事実…。
そんな時は
迷わず【害虫駆除】のプロに依頼しましょう!
プロならではの目線で
- 被害状況の確認
- 最適な駆除方法
- 侵入経路の封鎖
- 完璧な清掃・消毒
専門業者は多く存在しますが、中でも【害獣駆除110番】はスピーディーな対応と低価格で高評価を得ています!
現地調査や見積もりは無料で行ってくれますので、ネズミの被害を感じたら一度相談してみてはいかがでしょうか?
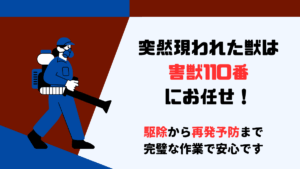
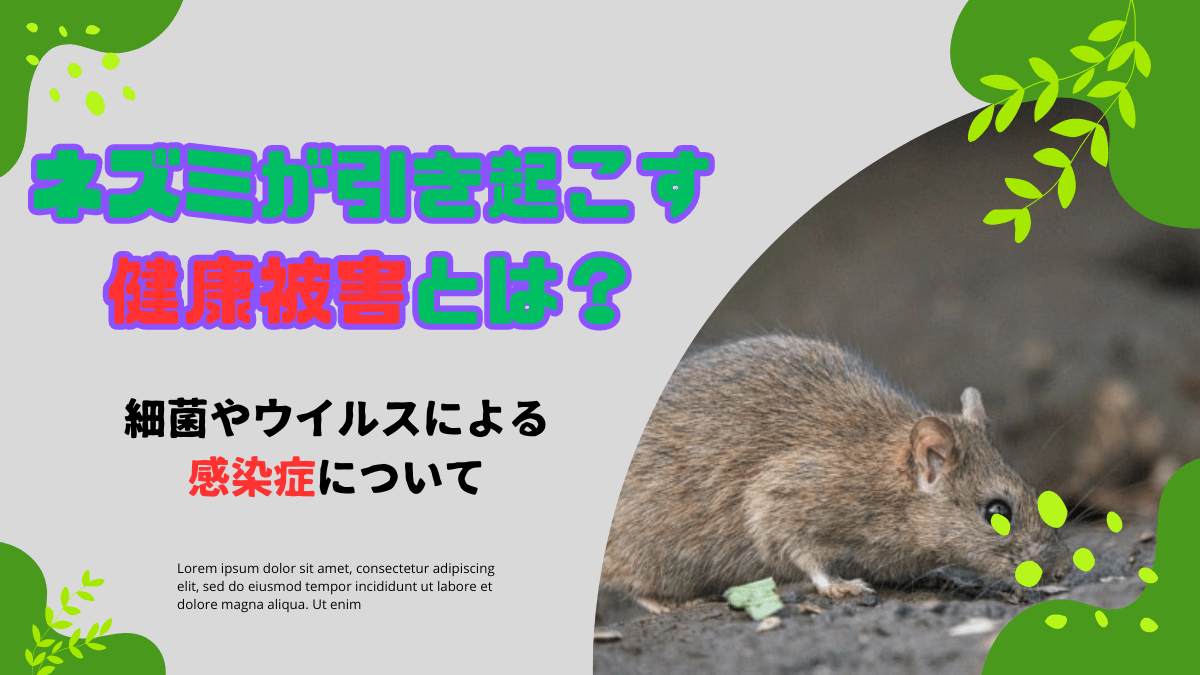
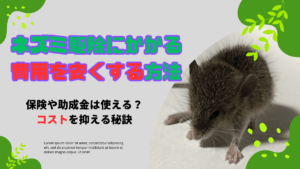
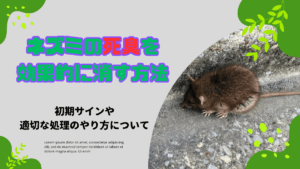
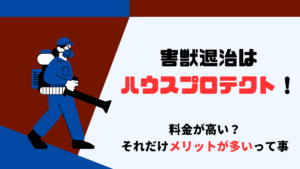
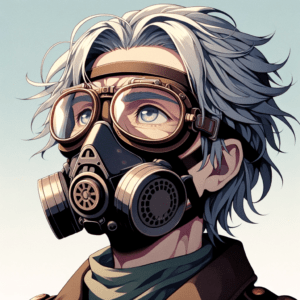
コメント